許されるのか?「人生に疲れたから安楽死」
デービッド・グドール氏。出身地の豪パースにて(2018年4月30日入手)。(c)AFP/EXIT INTERNATIONAL〔AFPBB News〕
2018年5月10日、スイスのバーゼルで、104歳になるオーストラリア人科学者デービッド・グドール氏が自殺幇助団体の介助を受けて自殺を遂げた。いわゆる「安楽死」である。
報道によれば、彼は植物学と生態学が専門でフィールドワークに研究者人生を捧げてきたのだが、高齢で車いす生活となり、視力も衰えてきた。屋外を自由に移動することもままならなくなり、数年前から「人生が楽しくなくなった」と感じるようになっていたという。
「人生終焉の法」
今や「人生100年時代」と言われる長寿社会になった。喜ばしいことではあるが、人々の寿命が伸びれば伸びるほど、彼のように「もう十分生きたし、人に迷惑をかけないで死にたい」とか、「生きるのに疲れた」「友人はもういない、新たな人間関係を作る気力がない」「このまま朝が来なければいいのに」と考える人が現れても、特段不思議なことではない。
しかし、自死することは簡単ではない。そこで、医師の手を借り、苦痛なく死に至る「安楽死」に対する関心が世界的に高まっている。
日本では、脚本家の橋田壽賀子さんが『安楽死で死なせて下さい』(文春新書)という本を書いて議論を巻き起こしたが、現実には、本人が望まない延命治療を控えたりあるいは中止したりする「尊厳死」の是非についても結論は出ていない。
一方、冒頭のオーストラリア人研究者が渡ったスイスのように、利己的動機でなければ、自殺幇助が罪に問われない国がある。さらに安楽死が合法化されているオランダ、ベルギー、ルクセンブルク、そしてカナダ。介助自殺はアメリカの一部の州でも「尊厳死法」という名前の法律で認められている。
安楽死を考える上で、これらの国々の法体系や実情を知ることは大きな意義がある。
なかでもオランダは、2001年に「要請に基づく生命の終結ならびに介助自殺法」(いわゆる「安楽死法」。注1)を制定した「安楽死先進国」である。
この法律が成立する前のオランダでは、「積極的安楽死」や「介助自殺」を施した医師は、いったん「嘱託殺人罪」で送検され、その手順が定められたガイドラインに沿ったものであったと認められた場合には不起訴になる、という仕組みになっていた。それが「安楽死法」制定により、注意深さの要件を守り、安楽死に手を貸し、届け出た医師は審査委員会(注2)により適切な措置だったと認められれば、送検されることはなくなったのである。
オランダは個人主義が強い国と言われる。自分の生き方は自分自身で決めるという国民性を持つ。そういう国だからこそ、「安楽死」を求める声も根強かった。
安楽死法の成立についても国民はおおむね歓迎してきたし、その運用についてこれまで大きな問題は発生してこなかった。
ところが近年、そのオランダで安楽死を巡る議論が再び盛んになっている。
倫理学を専門とする私は、長年安楽死についての調査・研究を続け、オランダの制度についても注目してきた。
オランダで一体何が起こっているのか。安楽死を巡る現状を調査すべく、私はオランダへ向かうことにした。
オランダで安楽死を巡る議論が再燃した理由の一つは、政府が議会に提出した「人生終焉の法案」の存在だった。
政権の枠組み変更でお蔵入り
「安楽死」が合法化されている国でも、希望すれば誰でも楽に死なせてくれる、というわけでは、もちろんない。「病気で耐え難い苦痛があるなら」死を介助してもらえる、ということだ。つまり重篤な病気に苦しんでいるわけではない人に、自死の介助を医師に要求する権利を与えているわけではない。
オランダでは安楽死が認められるためには、『本人の意思表示があること』『耐えがたい痛みがあること』『回復の見込みがないこと』『治療の代替手段がないこと』などが必須の条件になっている。
だが、その条件に当てはまらない人の中にも、「安楽死」を希望する人が数多く存在している事実がある。
自由に動けなくなった、軽い認知症の症状が出てきた、生きるのがしんどくなった、一人きりになった、これ以上生きて周囲に迷惑はかけたくない――理由は様々だろうが、「もう人生を終えたい」と思い詰めている人々もいるのだ。
こうした要請に応えるため、オランダ政府が用意したのが「人生終焉の法」の法案だった。2016年10月、保健大臣と法務大臣が署名したこの法案は、オランダの議会に提出された。
安楽死を推進する団体はこの法案を歓迎していた。世論の支持も見込めた。
国会で可決されれば、オランダの安楽死は、また一歩先に進むはずだった。
ところが、2017年3月の総選挙の結果、安楽死に反対の立場を取るキリスト教系の政党が政権に入り、新しい議会での法案の提出は難しくなった。どうやらこの法案は当分お蔵入りになるようだ。
この一連の動きの中で、安楽死の要件を緩和し、適応を拡大するかどうかの議論が沸き起こった。
オランダに出向いた私の取材にまず応じてくれたのは、安楽死審査委員会の委員を務めるマッコア教授だ。
私は「人生終焉の法」について、教授の意見を聞いた。
この法案に対しては、そもそも王立オランダ医師会をはじめ反対も多かった、という。
絶食や大量服薬で自死する「安楽死要請者」
マッコア教授が言う。
「第一に、信条として人生終焉の法それ自体に賛同しない人がいます。安楽死に反対している人からの批判だけではなくて、安楽死に肯定的で支持している人からも、この法律は好ましくないし、そもそも必要ないと制定に反対する意見が出ています。
他には、この法案が成立すると、患者が安楽死法の下に安楽死を行ったのか、それとも、人生終焉の法の下に安楽死を行ったのかが非常に不明瞭になる場合が想定されるので、人生終焉の法は制定すべきでないという意見もあります」
世論も賛成ばかりではなかったようだ。
だが一方で気になる調査結果にも出くわした。
2015年の調査委員会(注3)の調査によると、同年の安楽死要請者は1万2200人、安楽死数6822人だった。
問題は安楽死できなかった人たちだ。要請に応じてもらえなかった5500人のうち実に3000人もの人々が、絶食して餓死したり、溜めた薬を一気に飲んだりして自死したという。
さらに言うなら残りの約2500人は、安楽死を希望しながらも「要件を満たしていない」と判断され、放置されていることになる。
人生終焉の法は、彼らにとっては「救済」となるはずだった。この現状を改善する手立ては、今のところ用意されていない。
安楽死法の中で
この取材でもう一つ、注目すべき数値に出くわした。それは、安楽死審査委員会報告書の中にある安楽死した人の「医学的基礎的疾患」という項目の数値である。
安楽死で死を遂げた人々が抱えていた疾患で最も多いのは「がん」の70%だ。だがその表を眺めていると、2015年から「複合老人性疾患」という項目が新たに設定されていることに気づいた。従来からあった「複合性疾患」とは異なる項目だ。この新設の項目での安楽死の数が急増しているのである。
「複合老人性疾患」を理由とする安楽死は、2015年に183件、16年に244件、17年に293件と急激に数字を伸ばしている。
マッコア教授が解説してくれた。
「例えば『がんで心不全』、これは複合性疾患です。『難聴で、全盲で、変形性関節症で失禁』、これは『複合老人性疾患』となります」
高齢にもなれば誰しも、体のどこかには不調が出てくる。一つずつ取り上げれば、「耐え難く解放されない苦痛」ではないし、合理的な治療方法があるだろう。
しかし、その不調がいくつか重なると、「耐え難い解放されない苦しみ」と判断できる可能性が出てくるらしい。
「人生終焉の法」の成立は難しくなったが、以前よりも安楽死の要件が緩くなってきているのではないか――そんな疑念が湧いてきた。
安楽死数の変化を見ると、70歳以下ではそれほどの変化はないのに、70歳から80歳では、16年1831件、17年2002件、80歳から90歳の安楽死数は、16年1487件、17年1634件、90歳以上の安楽死数は16年522件、17年653件と、高齢者の安楽死が確実に増加している。「複合老人性疾患」が安楽死の要件として認められていることと無関係ではないだろう。
安楽死クリニック
ここでオランダの安楽死の実態を見てみよう。
オランダでは、「家庭医」制度が医療システムのすそ野を支えている。地域ごとに家庭医がいて、その地域の住民は体の不調がある時にはまずその家庭医に診てもらう。専門的な治療が必要と認められれば、家庭医から専門医が紹介される。
この家庭医は、継続的にその地域の住民の診察に当たっているため、住民にとっては病気や健康のこと以外の相談にも乗ってくれる尊敬すべき存在になっている。
そして、その住民が安楽死を望む場合、要請に応じるのもこの家庭医なのである。
患者が安楽死の要件を満たしていると判断されれば、患者の同意のもと、家庭医は患者の自宅で致死剤を注射し「積極的安楽死」を施すか、致死剤を処方し患者自身による「自死」を介助することになる。
しかし、中には患者の安楽死要請を納得しなかったり、そもそも信条において安楽死に反対の意見を持っていたりして、家庭医が引き受けないケースもある。その場合に患者が頼るのが「安楽死クリニック」だ。
2012年にハーグに設立された安楽死を専門に行うこのクリニックは、名前だけ聞くと「殺人病院」のようなイメージを受けるが、オランダの人々の間では肯定的に評価されている機関である。定年を迎えた家庭医などベテラン揃いの医療集団である。
 ハーグにある「安楽死クリニック」(筆者撮影)
ハーグにある「安楽死クリニック」(筆者撮影)医師と看護師から構成された機動力あるチームで、要請を受ければオランダ全土を移動し、患者と面談し、要件を満たせば安楽死を引き受ける。
ここでの安楽死の数も年々増えている。2012年32件、13年107件、14年227件、15年366件、16年487件、そして17年は751件という具合だ。
ここを頼ってくる人々の数もうなぎ上りであり、17年には安楽死の要請者は2500人に上った。そしてここでも「複合老人性疾患」を理由に安楽死を遂げている人が増えている実態が判明した。
安楽死の基礎的疾患が、16年、がん149件に対して、複合老人性疾患が116件と割合が多いのだ。
すなわち、本来なら近い将来に成立するかもしれない「人生終焉の法」の下で安楽死を要請するべき患者の一定部分が、現行の安楽死法の中で受け入れられているのではないだろうか。安楽死は本来の要件をかなり緩める形で運用され始めているのではないだろうか。そんな疑念を抱かざるを得ないのである。
グレーな案件
オランダでは安楽死法成立以降、大きなトラブルなくやってきたと述べた。それでもやはり15年も経つと、グレーな案件も浮かび上がってきている。
安楽死法が成立して以来、審査委員会が注意深さの要件に適合していなかったと判断を下したケースは、2017年までの16年間には100件あった。これは、その期間すべての報告された安楽死数5万5847件の0.18%である。
しかもそれら案件は、独立した第三者の医師に相談したのではなく、「友人の医師に診断を依頼した」とか、「専門医の診断を仰がなかった」という程度のものが多く、検察による訴追に至ったケースは1件もない。
マッコア教授も「この結果は、安楽死法を遵守する医師たちの努力によるものだろう」と評価する。
しかし最近になり、医師が訴追される可能性のある案件が2つ出た。
1件は、2016年に老人病院で認知症患者を安楽死させたケースだ。主治医が患者に対して、安楽死の最終意思の確認を怠り、腕を取って注射で死に至らせたという案件である。
患者は以前から安楽死を希望していた。そして、しかるべき時が来たので医師がその要請に従って患者に薬剤を注射しようとした瞬間に問題が起こった。
腕に針を刺した際に、患者が手をひっこめるそぶりをしたのだ。
手を引っ込めたという行動が、痛みに対してギョッとした反応からのものか、あるいは安楽死の拒否を意味したものなのか、その点が確認されていないことが問題視されているのだ。
もう1件は2017年の案件で、患者が検査と治療を拒否したことを、主治医が安楽死の要請と理解して安楽死を行ったケースである。この案件は耐え難い苦しみだったのか、また他の治療の選択肢はなかったのかという点が不明のケースである。
法に基づき厳格な運用を心掛けるべき医師の側も、「念には念を入れて」の気持ちが薄らいでいるのかもしれない。
緩和医療の遅れた実態
調査委員会による2015年報告書には、他にも気になる点があった。なんと、患者の意思を確認しないままでの安楽死が431件もあるという。
これは、どういうことだろうか?
実はこのケースは、医師が安楽死として届け出ていないケースだった。安楽死審査委員会にも報告されていない。担当医師は、「安楽死ではなく、緩和医療を行った」と理解しているために届け出なかった事例なのだ。
オランダには、安楽死ではなく、モルヒネを通して病状管理を強めることをよしとする医師が少なくない。その結果、患者の苦痛を緩和するためにモルヒネを多量に使用して死に至らせてしまうケースがあるのである。これは調査委員会から「グレー」として指摘されている行為だ。
オランダが安楽死法を立法した背景には、このようなグレーなケースを透明化する目的があったのだが、そこが十分機能していないのだ。
前述のように、オランダでは、安楽死法成立以前から医師の手で安楽死が行われていた。そのため医師たちは、緩和医療には積極的に取り組んでこなかったという歴史がある。
安楽死法ができてから、安楽死の手続きが煩雑なため、訴追されるのを恐れた医師たちや医療関係者が積極的にホスピスを増やし、遅ればせながら緩和医療の取り組みが始められた、というのが実態だ。そのためモルヒネの適正使用についての医師の認識も遅れていると言われている。
医師の判断だけで「尊厳死」
それでは延命治療を控えたり中止したりする、いわゆる尊厳死についてオランダではどう評価されているのだろうか。
日本では、2006年に富山県射水市の病院で、外科医が7人の患者から人工呼吸器を取り外した事件があった。結局不起訴になったが、これを契機として議論が起こり、患者の明示的な意思表明があれば、人工呼吸器の取り外しをした医師の責任を問わないという尊厳死法が国会に提出されようとしている。
私はかつて、オランダでの生命維持装置の取り外し・中止に関して医療関係者に質問したことがある。
彼が答えたところによると、オランダではそれは通常の医療の一環で、医師が判断さえしていれば全く問題にならないそうである。もちろん家族に説明し承諾を求めるが、家族はおおむね医師の判断を尊重するという。
日本では大問題になるのに、オランダでは全く問題にならいのはなぜなのだろうか。一つの理由は、オランダの医師が国民から信頼されているからだ。それだけ家庭医制度は国民の生活に根差したものになっているのである。
もう一つはオランダでは「脳死=人の死」の考えが定着しているからだろう。日本では「脳死=人の死」ではない。患者に臓器提供の意思がある場合にのみ、脳死判定を行うことができる。死を決めるのは医師でない。日本の臓器移植の始まりの際の不幸な事件(札幌医大心臓移植事件)が日本の医師の信頼を失わせたのかもしれない。
さらに言うなら、731部隊による人体実験が隠蔽されていた事実も大きいと思う。その結果、ナチスの医師たちの犯罪が徹底的に裁かれたドイツと異なり、医療に対する社会の監視システムが日本には生まれなかった。
日本の医療は、高度に専門化、分業化、技術化した結果、医師の「匿名化」まで進んでしまった。この医療システムにおいては、患者が自らの医師を人格的な相手として見いだすことは不可能なのではないだろうか。
家庭医制度が根付き、医師に自らの死を委ねることができるオランダでさえ、安楽死の実施状況には小さな綻びや揺らぎが見える。
医師への信頼感が生まれにくい日本の医療システムの中では、高齢化の中でいかに安楽死を望む人が増えようとも、制度として取り入れるのは容易なことではないだろう。
終末期医療に関心のある読者は以下の資料を参照されたい。丸善ホームページ内『世界の終末期医療の最新データ(盛永審一郎)』(https://www.maruzen-publishing.co.jp/info/n19241.html)
(注1)安楽死法。オランダでは、30年の議論の末2002年に、患者の自発的な意思があること、治療法のない病気であること、痛みが耐え難いことなど6つの要件を満たせば、安楽死を選ぶことができる法律が施行された。安楽死の希望者は、「家庭医」などとよく相談をし、さらに第三者の医師もそれを確認すると安楽死を実行に移せる。医師が致死薬を打つ『積極的安楽死』、医師から処方された薬を飲む『介助自殺』がある。2018年の安楽死審査委員会報告書では、2017年の安楽死の届け出件数は6585件(内訳6306が積極的安楽死、250が介助自殺, 29が両方)で、総死亡者数150,027人の4.4%だった。オランダのほかに、ベルギー(2002)、ルクセンブルク(2009)、そしてカナダ(2016)にも同様の法がある。
(注2)安楽死審査委員会。安楽死法第3章に基づいて設置された安楽死の裁定を行う公的機関。毎年年次報告書を発行。安楽死を行った医師の届け出書類を審査して、注意深さの要件が適切に守られたかどうかを審査する。
(注3)調査委員会(レメリンク委員会)。1990年にオランダ政府によって設置された調査グループで、安楽死法が良好に機能しているかを調査するために5年ごとに死亡診断書に基づく全国的規模での調査を行う委員会。
(注4)一般医ともいう。オランダの医療は家庭医制度から成り立っている。この地区にはこの家庭医となっている。1人の家庭医が2800人ぐらいの住民を担当している。まず不調があれば、家庭医に診てもらう。薬だけで治る病気は、家庭医が診るが、それ以上の場合は専門医を紹介してくれる。その専門医での治療が終わるとカルテは家庭医のところにバックされる。つまりその人の体を何十年と管理してくれるシステムである。健康面だけでなく、心の相談、教育何でもありだ。だから患者との間に信頼関係がある。最後はこの先生にというわけである。オランダの安楽死の担当医は2017年においても86%が家庭医(ホームドクター)である。
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/53441
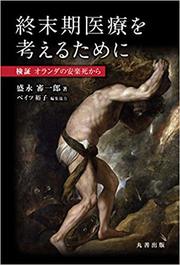
0 件のコメント:
コメントを投稿